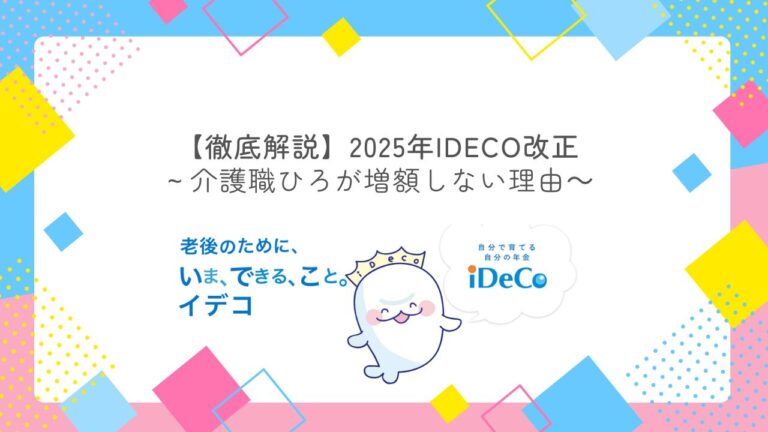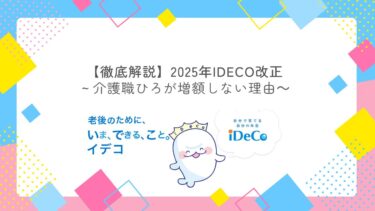こんにちは、介護職ひろです。
「iDeCoが改正されるって聞いたけど、結局どう変わるの?」
「掛金の上限が上がるらしいけど、増額した方がいいのかな?」
2025年の税制改正大綱でiDeCoの大幅な制度変更が発表され、話題になっていますよね。
私も現在、月23,000円をiDeCoに拠出しています。今回の改正で上限額が大幅に引き上げられることになりましたが、我が家は増額しないことに決めました。
【この記事の結論】
✅ iDeCo改正で掛金上限が月62,000円に(2027年〜)
✅ ただし10年ルールへの改悪もあり要注意
✅ 我が家は「新NISA優先」で増額しない判断
✅ 住宅ローン控除がある人は節税効果が約35%減
– 掛金上限額がどれくらい引き上げられるか
– 「5年ルール→10年ルール」の改悪と言われるポイント
– 我が家がiDeCoを増額しないと決めた4つの理由
– 増額を検討すべき人・しなくていい人の特徴
iDeCo 2025年改正の全体像

まず、iDeCoの改正スケジュールを整理しておきましょう。
| 時期 | 改正内容 |
|---|---|
| 2024年12月 | 事業主証明書の廃止、企業年金加入者の上限額変更 |
| 2026年1月 | 退職所得控除「5年ルール→10年ルール」変更 |
| 2027年1月予定 | 掛金上限額の引き上げ、加入可能年齢70歳へ拡大 |
ニュースでは「2025年改正」と言われていますが、実際に掛金上限額が変わるのは2027年1月からの予定です。
厚生労働省は「2027年の控除分からの実現を目指して準備を進める」としています。
では、具体的な改正内容を見ていきましょう。
そもそもiDeCoの加入率ってどれくらい?
改正内容に入る前に、実際どれくらいの人がiDeCoに加入しているのか確認しておきましょう。
全国の加入率は約5.4%
2025年3月末時点のiDeCo加入者数は約363万人。公的年金被保険者全体に占める加入率は約5.4%です。
| 加入者区分 | 加入者数 | 加入率 |
|---|---|---|
| 第1号(自営業者等) | 約37.6万人 | 約2.8% |
| 第2号(会社員・公務員) | 約309.3万人 | 約6.5% |
| 第3号(専業主婦等) | 約15.4万人 | 約2.3% |
会社員・公務員の加入率は約6.5%と比較的高めですが、それでも10人に1人も加入していないのが現状です。
私の職場(九州の特養)での実感
参考までに、私が勤務している九州の特別養護老人ホームの状況をお伝えします。
正規職員約50名のうち、iDeCo加入者は3名程度です。
つまり、加入率は6%程度。全国平均くらいですが、それでも「ほとんどの人がやっていない」というのが実感です。
介護職の場合、以下の理由でiDeCoに踏み出せない人が多いのではないかと思います。
– 給料が高くないので毎月の掛金を捻出するのが難しい
– 60歳まで引き出せないのが不安
– そもそもiDeCoの存在を知らない
– 手続きが面倒そう(2024年12月から簡素化されました)
2024年12月の改正で事業主証明書が不要になったので、今後は加入のハードルが下がって増えていくかもしれませんね。
iDeCo改正4つのポイント
それでは今回の改正の4つのポイントを順番にみていきます。
【改正ポイント①】掛金上限額の引き上げ
今回の改正で最も注目されているのが、掛金上限額の引き上げです。
改正前後の上限額比較
| 加入者区分 | 改正前(現行) | 改正後(2027年〜) |
|---|---|---|
| 自営業者・フリーランス | 月68,000円 | 月75,000円 |
| 会社員(企業年金なし) | 月23,000円 | 月62,000円 |
| 会社員(企業年金あり) | 月20,000円上限 | 上限撤廃(月62,000円まで) |
| 公務員 | 月12,000円 | 月54,000円程度 |
| 専業主婦(夫) | 月23,000円 | 変更なし |
※企業年金ありの会社員は、企業年金との合計で月62,000円まで
特に企業年金のない会社員は、月23,000円→月62,000円と大幅に引き上げられます。
私のように企業年金のない会社で働いている人にとっては、選択肢が大きく広がることになりますね。
節税効果はどれくらい変わる?
掛金が増えると、所得控除の額も増えます。
例えば年収400万円の会社員の場合(概算):
– 現行(月23,000円):年間約41,400円の節税
– 改正後(月62,000円拠出した場合):年間約111,600円の節税
年間で約7万円も節税額が増える計算です。
ただし、これは「満額拠出した場合」の話。後ほど説明しますが、増額するかどうかは各家庭の状況次第です。
【改正ポイント②】加入可能年齢が70歳未満に拡大
これまでiDeCoの加入年齢は以下のとおりでした。
– 自営業者など:60歳未満まで
– 会社員・公務員:65歳未満まで
改正後は、働き方に関わらず70歳未満まで加入可能になります。
加入年齢拡大のメリット
– 60歳以降も働く人が増えている現状に対応
– より長期間、税制優遇を受けながら積み立てできる
– 複利効果による資産増加が期待できる
定年延長や再雇用で65歳以降も働く方が増えていますよね。そういった方にとっては、老後資金の準備期間が延びるのは嬉しい改正です。
【改正ポイント③】退職所得控除「5年ルール」が「10年ルール」に【改悪】
ここが「iDeCo改悪」と言われているポイントです。
そもそも退職所得控除とは?
iDeCoを一時金で受け取る場合、「退職所得控除」という税制優遇があります。
退職所得控除の金額:
– 加入20年以下:40万円×加入年数
– 加入20年超:800万円+70万円×(加入年数−20年)
例えば30年加入していれば、800万円+70万円×10年=1,500万円まで非課税で受け取れます。
「5年ルール」から「10年ルール」への変更
改正前(5年ルール)
iDeCoの一時金を受け取った後、5年以上空けて退職金を受け取れば、それぞれに退職所得控除が適用できました。
例:60歳でiDeCo一時金 → 65歳で退職金 → 両方に控除適用OK
改正後(10年ルール)
iDeCoの一時金を受け取った後、10年以上空けないと、退職金の控除が満額適用されなくなります。
例:60歳でiDeCo一時金 → 65歳で退職金 → 控除が一部重複してしまう
2026年1月から適用
この「10年ルール」は2026年1月から適用されます。
ただし、2025年中にiDeCoの一時金を受け取った場合は従来どおり「5年ルール」が適用されます。
正直なところ、我が家はこの改正の影響をあまり受けません。
理由は後ほど詳しく説明しますが、40歳で転職しており退職金がまとまった金額にならない見込みだからです。
そもそも介護業界は退職金を余り期待できず、私が13年勤務した前の職場では退職金額は曖昧でしたが30万もありませんでした・・。大手企業だとニュースで退職金1000万以上とか聞くことありますが、介護業界でそこまで手厚い企業はまれだと思います。
【改正ポイント④】事業主証明書の廃止(2024年12月施行済み)
これは既に施行されている改正です。
改正前の手続き
会社員がiDeCoに加入する場合、勤務先の事業主から「事業主証明書」に証明印をもらう必要がありました。
これが結構面倒で、加入のハードルになっていたんですよね。
改正後の手続き
2024年12月から、個人口座から掛金を拠出する場合は事業主証明書が原則不要になりました。
自分だけで必要書類を準備できるようになり、加入手続きが大幅に簡単になっています。
※給与天引き(事業主払込)を選択する場合は、引き続き事業主証明書が必要です。
我が家がiDeCoを「増額しない」と判断した4つの理由
ここからは、我が家の実体験をお話しします。
今回の改正で掛金上限が月62,000円まで引き上げられますが、我が家は現在の月23,000円から増額しないことに決めました。
その理由は以下の4つです。
理由①:新NISAの枠を埋められていない
我が家の投資状況はこんな感じです。
– 私(夫):新NISAつみたて投資枠+成長投資枠を活用中
– 妻:新NISAつみたて投資枠で毎月3万円
ただ、年間360万円の枠を毎年使い切れているかというと、正直まだまだです。
iDeCoよりも新NISAを優先すべき理由
| 項目 | iDeCo | 新NISA |
|---|---|---|
| 資金の引き出し | 60歳まで原則不可 | いつでも可能 |
| 所得控除 | あり | なし |
| 運用益非課税 | あり | あり |
| 受取時の課税 | あり(控除後) | なし |
iDeCoは所得控除のメリットがありますが、60歳まで引き出せないのが最大のデメリット。
新NISAなら必要なときに引き出せるので、まずは新NISAの枠を優先的に使うようにしています。
理由②:子供が3人いて教育費の心配がある
我が家は長女10歳、次女6歳、長男3歳の3人の子供がいます。
これから教育費がどんどんかかってくる時期です。
– 長女:あと8年で大学進学
– 次女:あと12年で大学進学
– 長男:あと15年で大学進学
3人が大学に通う時期が重なると、年間の教育費負担はかなり大きくなります。
iDeCoに入れたお金は60歳まで引き出せません。
もし教育費が想定以上にかかった場合、iDeCoのお金は使えないんですよね。
子供3人の教育費を考えると、資金が拘束されるiDeCoへの追加投資は不安があります。
だからこそ、いつでも引き出せる新NISAを優先しています。
理由③:住宅ローン控除があるので節税効果が薄い
我が家は住宅ローン控除を受けています。
住宅ローン控除で所得税・住民税がかなり減っているので、iDeCoの所得控除を増やしても恩恵が限られるんですよね。
介護職の平均的な年収(300〜400万円)で、住宅ローン控除がある場合とない場合でiDeCoの節税効果がどう変わるか見てみましょう。
【年収400万円・住宅ローン控除なしの場合】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所得税額(概算) | 約6.7万円 |
| 住民税額(概算) | 約14.2万円 |
| iDeCo節税効果(月23,000円拠出) | 約4.1万円/年 |
iDeCoの掛金27.6万円(月23,000円×12ヶ月)が所得控除になり、所得税率10%で約2.76万円、住民税10%で約2.76万円、合計で約4〜5万円の節税になります。
【年収400万円・住宅ローン控除ありの場合】
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 住宅ローン控除額(残高3,000万円の場合) | 約21万円 |
| 控除後の所得税 | 0円(控除で相殺) |
| iDeCo節税効果 | 約2.7万円/年(住民税分のみ) |
住宅ローン控除で所得税が0円になっている場合、iDeCoの節税効果は住民税分の約2.7万円だけになります。
つまり、住宅ローン控除があると、iDeCoの節税効果が約35%減少してしまうんです。
【年収300万円の場合はさらに厳しい】
年収300万円だと所得税額は約3.6万円、住民税額は約8万円程度。住宅ローン控除で所得税がほぼ0円になるケースが多いため、iDeCoの節税効果はほぼ住民税分のみ(約2.7万円/年)に限られます。
もちろん、住宅ローン控除には期限があります(最長13年)。控除期間が終わればiDeCoの節税効果がフルに発揮されるので、長期的に見ればメリットはあります。
ただ、今の時点で「節税効果が薄いのに60歳まで資金拘束される」のはリスクが高いと判断しました。
iDeCoの節税効果を最大限に活かせるのは、以下のような方です。
– 住宅ローン控除がない(または終わっている)
– ふるさと納税の枠にまだ余裕がある
– 課税所得が高い
我が家の場合、住宅ローン控除だけでかなり税金が減っているので、これ以上iDeCoを増やしても効果が薄いと判断しました。
理由④:退職金がまとまった金額にならない見込み
私は40歳で介護業界に転職しました。
仮に60歳まで今の会社に勤めたとしても、勤続20年です。
特養の生活相談員として働いていますが、介護業界の退職金は一般企業に比べると控えめ。まとまった金額にはならない見込みです。
また、60歳以降はブログやパートなど、好きなことをしながら生活していければいいなと考えています。
つまり、「10年ルール」への変更で退職所得控除の二重取りができなくなっても、そもそも退職金自体が大きくないので影響は小さいんです。
iDeCoの増額を検討すべき人・しなくていい人
ここまでの内容を踏まえて、増額を検討すべき人としなくていい人をまとめます。
増額を検討すべき人
✅ 新NISAの年間360万円枠を使い切っている
→ 余剰資金があるならiDeCo増額も選択肢
✅ 課税所得が高い(年収600万円以上目安)
→ 所得控除のメリットが大きい
✅ 住宅ローン控除がない・終わっている
→ iDeCoの節税効果をフルに活かせる
✅ 子供がいない、または教育費のピークを過ぎた
→ 60歳まで資金拘束されても問題ない
✅ 60歳以降も働く予定で収入がある
→ 加入期間が延びて複利効果アップ
増額しなくていい人
❌ 新NISAの枠をまだ使い切れていない
→ まずは新NISA優先!
❌ 住宅ローン控除を受けている
→ 節税効果が限られる
❌ 子供の教育費がこれからかかる
→ 資金拘束のリスクを避けたい
❌ 60歳前にまとまった資金が必要になる可能性がある
→ iDeCoは途中引き出し不可
❌ 退職金が少ない見込み
→ 退職所得控除の恩恵が小さい
FAQ(よくある質問)
Q. iDeCoと新NISA、どっちを優先すべき?
A. 資金の流動性を考えると、まず新NISA優先がおすすめ。
Q. 住宅ローン控除があってもiDeCoのメリットはある?
A. 住民税分の節税(約2.7万円/年)は受けられる。
Q. 2027年まで待った方がいい?
A. 今から始めても問題なし。掛金は後から増額できる。
妻はiDeCoをやっていない理由
ちなみに、妻はiDeCoをやっていません。
妻の投資は新NISAのつみたて投資枠で毎月3万円のみです。
理由はシンプルで、我が家の家計状況では、まず新NISAを優先した方がいいと判断したからです。
2. 家計の流動性を確保したい
3. 投資に前向きではない
将来的に余裕ができたら検討するかもしれませんが、資産運用には興味がないので今は新NISAでつみたてしてくれてるだけで十分に凄いことだと思っています。
まとめ:改正内容を理解した上で自分に合った選択を
iDeCo 2025年改正のポイントをまとめます。
【2024年12月施行済み】
– 事業主証明書の廃止(手続き簡素化)
【2026年1月から】
– 退職所得控除「5年ルール→10年ルール」へ変更
【2027年1月予定】
– 掛金上限額の大幅引き上げ(会社員:月23,000円→月62,000円など)
– 加入可能年齢が70歳未満に拡大
改正で選択肢が広がるのは嬉しいですが、「上限が上がったから増額しよう」と安易に決めるのは危険です。
2. 子供3人の教育費が心配で資金拘束が不安
3. 住宅ローン控除があり節税効果が薄い
4. 退職金がまとまった金額にならない見込み
大切なのは、自分の家庭の状況に合った選択をすることです。
「新NISAとiDeCo、どちらを優先すべき?」
「増額して大丈夫かな?」
迷ったときは、まず新NISAを優先し、それでも余裕があればiDeCo増額を検討するのがおすすめです。
将来の自分への仕送りだと思って、無理のない範囲でコツコツ続けていきましょう!
最後まで読んでくださりありがとうございました。
少しでも参考になれば嬉しいです。